憲法9条により、自衛隊は軍隊として認められず、その活動も軍事行動であってはならない。
2019年12月27日の閣議で、中東海域での航行の安全確保のため、海自護衛艦の独自派遣が決定されました。
中東海域で、日本船籍含む民間のタンカーなどが襲われる可能性があり、日本も”武器使用”を伴う海上警備行動を発令し、「不測の事態」に対処するといいます。
ですが、派遣の根拠は、防衛省設置法による情報収集目的を名目とした「調査・研究」。ですが、もはや「調査・研究」段階ではないでしょう。武器使用が当然求められる事態なのです。
なぜ自衛隊はいつも迅速かつ必要な行動が取れないのか。
自衛隊を機能不全にする憲法9条、海上警備行動や防衛出動とは何なのか。警察と軍隊の違いは?自衛権行使新3要件とは?自衛隊の現状、問題点をわかりやすく解説していきます。
憲法9条と自衛隊
憲法9条は、軍隊も交戦権も放棄・否認していますので、自衛隊は存在自体がグレー。自衛隊の活動は常に法的根拠が曖昧です。法的には軍隊が存在しないのですから、当然軍事活動だって存在してはいけません。
2020年の自衛隊の中東派遣も、民間船舶護衛など軍事目的として派遣すると憲法違反状態に。
法的根拠を防衛省設置法第4条の18〔調査・研究〕で説明することになりました。
第1条(目的)この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする
第4条 防衛省は次に掲げる事務をつかさどる。(その18) 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと
引用元:防衛省設置法
本来は、憲法9条を改正あるいは破棄し、自衛隊を軍隊とし、その軍事活動に法的根拠を与えるべきです。
法的根拠が不明確なまま現地に派遣される自衛隊員は、現地で苦しい立場に置かれることになります。法的根拠が不明確とは「なにをどこまでしてよいのか?」(交戦規定)という線引きがよくわからないということ。
日本では、交戦規定すら議論をタブーされています。日本は軍隊を持たず、交戦権を否認しているのだから、交戦規定など議論したら憲法違反だというのです。
海上警備行動で何ができるの?
中東派遣では、調査・研究名目で派遣された海自護衛艦。いざとなれば海上警備行動さえ発令するとありますが、この海上警備行動とは何でしょうか。
自衛隊法第82条(海上警備行動)は「海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため必要がある場合は、内閣総理大臣の承認を経て海自は必要な行動を取れる」
ですが、海上警備行動はあくまでも警察権での対処であり、その武器使用は正当防衛や緊急避難しか認められておりません。
海上警備行動はもともと日本の管轄区域での活動が想定されています。日本の警察と同じです。
したがって、ホルムズ海峡付近で外国船舶が襲われている場合、日本の自衛隊は救助に向かえません。無線やスピーカーで警告するくらいの行動しか出来ないというのが防衛省の見解です。
かえって国際社会での日本の信用を低下させてしまうのではないでしょうか。
軍隊と警察の違いとは
自衛隊中東派遣で外国船舶はともかく、自国船舶は守れるのでしょうか。解答はNOです。無線やスピーカーでの警告しか出来ない海上警備行動で守れるわけがありません。
大手メディアも全く報道しませんが、まず警察と軍隊との違いです。
軍艦など装備の点もそうですが、法的にまったく性質が違います。軍隊と言うのは国際法とても大きな権限が与えられています。
たとえば、尖閣諸島で対立する日本と中国。中国は、2018年7月に中国版海上保安庁の艦船部隊を軍事組織の傘下に入れました。
大手メディアは「日本への圧力を高めてきた」と報じていますが、若干中国の意図するところを間違えています。
中国は、これまで海警局(海上警察)を用い、日本の海上保安庁のような権限で活動していました。それを軍隊の行動とすることになったのです。決定的に事態を変えます。
国際法上、軍隊は公船に対して撃沈する権限を唯一与えられております。一方、警察は、自国内での法執行活動しかできません。自国の法律の範囲外に対して何もできません。
つまり、明らかに外国の公的な任務を帯びており、その国の主権に基づいて行われている活動や対象には何もできないのです。警告を与えるのみ。
ですから、中国は今後、海上保安庁の船を撃沈できる法的根拠を、海警局などの自国船舶に与えたのです。
一方、自衛隊の海上警備行動は警察権での行動・対処。もし、海上保安庁の手に余り、自衛隊に出動を要請した場合でも、中国の海警局(軍隊)に対抗できません。
軍隊を持たない日本の致命的ミス
中東派遣では、もしイランなど外国の公船や軍隊に襲撃されたら、海上警備行動(警察活動)で対処する自衛隊が一歩も二歩も出遅れます。国籍不明の海賊や民間の武装勢力に対しては実力行使は可能かもしれませんが、その判断が出来ません。
米国は明らかに「イランが関与している」「イランの国軍が動いている」と主張しています。つまり、海賊と思ったら国軍だったということもありえるのです。
そのような混沌とした状況では、どこの国も、国際法的に最強の権限を有する軍隊を派遣します。軍隊であれば、警察と違って、他国の軍隊・公的組織を堂々と攻撃できるからです。
日本は国際社会のきわめて初歩的な問題に対し、0点解答をしています。自衛隊という「警察力」で対処しようとしているのですから。まったく対応できません。
日本国民の皆さんの中には、軍隊など持たなくてもいいと今まで思われていた方はたくさんおられると思います。しかし、国際法上で最強の権限を与えられている”軍隊”を持たないのは、国際社会での致命的ミス。
国際社会には、警察力では絶対に対処できない法的領域があります。そのため、諸外国は軍隊を保有しています。軍隊を別に危険な存在とは思っておらず、必要だから保有しています。
防衛出動で何ができるの?
自衛隊も防衛出動により「軍事行動」が認められているという見方もあります。
日本では、自衛隊法第76条1項にて総理大臣の承認を経て防衛出動命令を発し、自衛隊法第88条にて我が国を防衛するための武力行使を行える、とあります。
武力行使は国際法上の自衛権によってのみ正当化される。それはいい。
日本の問題点は、自衛権行使のルールを、今では死文化されている国連憲章第51条の武力攻撃発生時のみに限っていること。また自衛権行使を国内法と整合する形で、必要以上に厳格化していること。
自衛権行使の新三要件とは? 問題点はどこ?
安倍内閣が、2014年7月1日に閣議決定した自衛権の新三要件の一つは、
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
自衛権の三要件とは、自衛権を行使する場合の条件のことです。まったく国際音痴。
国際社会では、自衛権行使のルールはもっとシンプルです。必要性と均衡性の原則。それだけ。
必要性の原則とは、軍隊でしか対処できないような事態、あるいは緊急性があり軍隊でしか対応できないときに発動する。均衡性の原則とは、その軍事行動が他国のそれと比べ過剰にならないように発動する。
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」など、まったく意味が分かりません。
いつどのように自衛権行使するのか、そもそも公表するものではありません。
「我が国は国際法上の自衛権に従って、武力行使をします」諸外国はこれしか言いません。当たり前。日本政府が外交音痴・国際音痴と笑われるのは当然です。
自衛権行使を現場の兵士から取り上げる日本政府??
自衛権は自国軍の兵士が現場で活動する法的根拠でもあります。たとえば、兵士が戦場で敵に遭遇したら、銃撃し撃退します。
その法的根拠になるものが、各兵士に与えられている自衛権です。にもかかわらず、国際音痴の日本政府は、
憲法上、建前としては、日本に軍隊も兵士も存在しません。だから兵士に対する自衛権などそもそも考えていません。自衛権は、本来では行使する機会がまったく存在しえないものでして、一般の兵士から取り上げて、自分たち政府が自衛権はとりあえず○○なものと決めてみました。ちなみに、○○は私たちもよくわかっておりません笑
アメリカなどは、作戦ごとに交戦規定を定め、最前線の兵士ひとりひとりに行使しうる自衛権を説明しております。つまり、「こういう場合には撃ってもよい」というルールです。
また、交戦規定を一枚のカードにして、個々の兵士に持たせている。諸外国では当たり前のこと。
100年前の軍事的状況を想定する日本政府
日本政府の自衛権行使の新三要件は、死文化している国連憲章第51条の武力攻撃を要件に含めています。
日本政府は、「武力攻撃とは何十万もの敵国軍隊が攻めてくるような状況である」と、もはや100年以上前の国際社会でのみ通用する見解をかかげております。
現代では、弾道ミサイルが飛び交うような戦い。「何十万もの敵国軍隊の侵攻」が開戦の合図となる状況は起こりえないし、それを武力攻撃と認定するのであれば、日本の反撃は決定的に遅れてしまいます。
議論の内容があまりにも古い。日本の海上警備行動も防衛出動も現代の国際社会ではまったく通用しません。日本船舶も日本国の安全もなに一つ守れないでしょう。
まとめ
憲法9条により法的には「軍隊」が存在しない日本。軍事行動も存在してはいけない。自衛隊という組織が法的にグレー。自衛隊は軍隊よりも警察に近い。
海自による海上警備行動も、警察権の行使。軍事行動ですらない。外国軍隊や公船には対処できない。国際法上、軍隊や公船相手には対処する権限は軍隊にのみ与えられている。自衛隊には対処不可。
自衛隊法第76条、第88条の防衛出動による自衛権行使は100年以上前の軍事状況を想定しています。
「何十万もの敵国軍隊が押し寄せてきた場合」という武力攻撃発生を防衛出動の条件としている。自衛隊の初動が遅れてしまう。現在の戦略ミサイルが十数分で飛んでくるような状況では、まともな自衛権行使すらできない。
国際法上、軍隊と警察はその機能・権限が大きく違う。自衛隊を「軍隊ではない別種の組織」と定めるのは、国際的にデメリット。
安倍内閣が、2014年7月1日に閣議決定した自衛権行使・新三要件も、国際法上の自衛権行使とかけ離れている。諸外国では「我が国は国際法上の自衛権に従って、武力行使をします」というのが普通。
日本のように、”国内法上の自衛権が〇〇であって”など、どうのこうのと言わない。まったくのナンセンス。
憲法上、軍隊を持たない戦後日本は、交戦規定も不明確。中東派遣などの自衛隊の海外派兵のケースでは慌てふためく自衛隊。
もし外国軍あるいは諸外国の公的な組織に、民間人・民間船舶が襲われても、警察力に近い自衛隊では必要な反撃が出来ない。民間船舶などが逃走する時間稼ぎしか出来ません。
諸外国は、軍隊が国際社会で必要だからこそ保持しています。日本も自衛隊を日本軍と改め、軍隊とし、国際社会の問題に軍隊をもって対応すべきでしょう(了)。

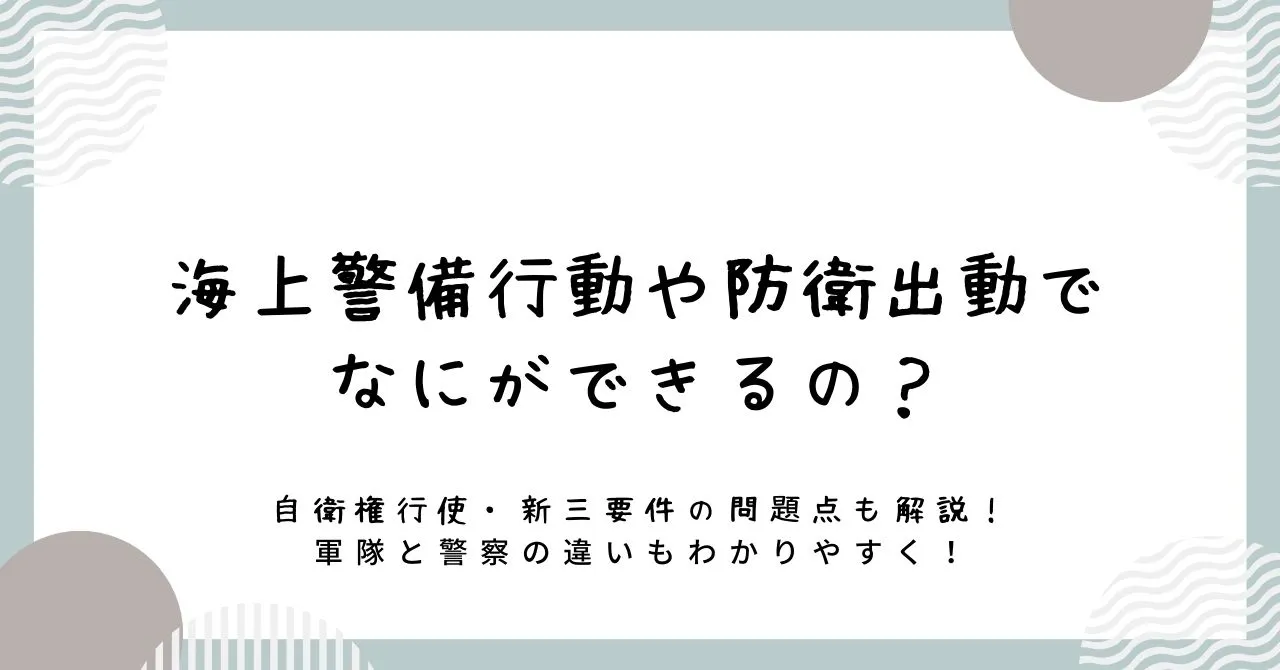


コメント