「日本国憲法は、法的に考えますと無効となるのが正しいと思うのですが、その点はいかがお考えでしょうか」5月の憲法記念日の集会。国会議員と出席者の質疑応答の時間。出席者の質問です。
この質問に対し、壇上の国会議員や地方議員は困惑するばかり。
「えー、そういう議論もありますが、そのー、今ではあまり主張されないものでして。日本国憲法がすでに定着していることを踏まえても、その議論に意味はあまりないかと思います」
と答えました。質問者の方は納得いかない顔でした。質問自体に答えていないからです。
「もうべつにそんなこと質問してこなくてもいいだろうが」と舌打ちした国会議員もいました。
しかし、この質問は「米占領軍が強要した日本国憲法をはたして、このまま認めてよいのだろうか」という重要な問題提起。
日本国憲法無効論は、議論さえ忌避されている感があります。研究者の著書で日本国憲法無効論がかろうじて論じられるくらいでしょうか。
一方、日本国憲法有効論に関しては8月革命説という政治的主張のみ存在します。
こちらの記事では、日本国憲法無効論についてわかりやすく説明していきたいと思います。
国際法上から見た日本国憲法無効論の是非
国際法上からの日本国憲法無効論と国内法上からの日本国憲法無効論。大きく分けてこの二つ。
まずは国際法上からの日本国憲法無効論の是非を検証していきます。
1907年ハーグ陸戦条約を破ったアメリカの国際法違反
国際法上からの日本国憲法無効論は、国際条約に違反して日本国憲法が制定されたものだから無効という主張。
当時、日米が締結していた国際条約では、はっきりと日本国憲法が無効であると記載があります。
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なきかぎり、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保するためなしうべき一切の手段をつくすべし
引用元:「陸戦の法規慣例に関する条約(1907年ハーグ陸戦条約)」の条約付属書「陸戦の法規慣例に関する規則」第43条(占領地の法律の尊重)
つまり、アメリカは占領地の法律を尊重する義務を逸脱し、日本国憲法を制定したので、その制定過程に不備があるために無効だとするもの。
そして、休戦条約として結んだポツダム宣言第10項には「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし」という文言のみしかありません。
大日本帝国憲法が障害にあたり、改正が必要だという記載はありませんでした。米占領軍の強行による日本国憲法への改正は、1907年ハーグ陸戦条約に違反する、国際法違反行為となります。
”特別法は一般法を破る”条約法条約第59条から考えてみても
ですが、ポツダム宣言に明確に「大日本帝国憲法を変える」という記載さえあれば、国際法上は全く問題がありませんでした。国際法の世界には「特別法は一般法を破る」という原則があります。
条約法に関するウィーン条約(1969年採択)第59条に同じものがあります。本条約は、国際条約を結ぶ際のルールを定めた条約。国際慣習法とされていたものを、成文法として条約文の形にしたものです。
つまり、第二次世界大戦以前は国際慣習法として機能していたもの。
国際慣習法とは、国家が必ず守らなければならないルールのこと。一方で、成文法は、その国際条約を締結した当事国のみに適用されるものです。二つ合わせて国際法を構成しています。
日本も批准しており、当事国は100か国を超える普遍的な条約です。その第59条を参考のために以下に記載いたします。
第59条(後の条約の締結による条約の終了又は運用停止)
1 条約は、すべての当事国が同一の事項に関し後の条約を締結する場合において次のいずれかの条件が満たされるときは、終了したものと見なす。 (a)当事国が当該事項を後の条約によって規律することを意図していたことが後の条約自体から明らかであるか又は他の方法によって確認されるかのいずれかであること。(b)条約と後の条約とが著しく相いれないものであるためこれらの条約を同時に適用することが出来ないこと
2 当事国が条約の適用を停止することのみを意図していたことが後の条約自体から明らかである場合又は他の方法によって確認される場合には、条約は、運用を停止されるにとどまるものとみなす
繰り返しますが、ポツダム宣言に「大日本帝国憲法が、占領する上での絶対的な障害となっており、これを改変する」と明記されていればよかったのです。
となれば、アメリカは日本占領において1907年ハーグ陸戦条約第43条の拘束から解かれる可能性もあります。しかし、ポツダム宣言に記されていない以上、アメリカの明らかな国際法違反です。
ハーグ陸戦条約条文”占領するうえでの絶対的支障”とは
ハーグ陸戦条約では、第46条に私権の尊重、第47条に略奪の禁止も定められており、
第43条における絶対的な支障とは、例えば占領軍が占領地を通過する上での道路法適用免除であるとか、その程度の法律不適用が認識されていました。
ましてや、第43条の条文中に”占領地の現行の法律を尊重する義務”があるのですから、その国の根本法たる憲法を改変することは許されるわけがない。
アメリカも、建前としては日本の立法府を裏で管理・監督するというやり方で明治憲法を破棄しました。
とはいっても、第43条は当然そのような状況を想定していたため、条文中にわざわざ「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は」と条文の中に規定しております。
これが国際法上における日本国憲法無効論です。
国内法上から見た日本国憲法無効論の是非
2つ目に、国内法上から見た日本国憲法無効論について解説します。
まず前提知識として、憲法学には、「憲法改正に限界があるのか」という憲法学の議論があります。
一般に、限界を認める憲法改正限界説が通説であり、それゆえ、日本国憲法も平和主義・国民主権・基本的人権の尊重などの憲法の大原則に関しては改変を許されておりません。
憲法改正限界説は、大日本帝国憲法にも適用され、制憲権の帰属や国体、欽定憲法など帝国憲法の大原則を超える改正は認められません。
実は、日本国憲法の正式名称は「大日本帝国憲法の昭和21年改正」です。
ですから、国民主権や国体に関する条文の削除など、このような限界を超えた改正は無効といえます。
大日本帝国憲法のどの条項がどのように変更されたかも不明。例えば、第○条を次の通り改正する、などという記載が一切ない。
形式的にも実質的にも改正とは認められず、一方で「大日本帝国憲法を破棄した」と当時の立法府が宣言した事実もありません。これが憲法改正限界説からの日本国憲法無効論です。
もう一歩進んだ議論をすると、現在も大日本帝国憲法こそが日本の実質的な憲法として存在するということです。
憲法学者も日本国憲法は実際は無効だと考えている
日本国憲法改正を語る前提として、そもそも占領下の日本で米軍が作った日本国憲法を認めてよいのかという問題があります。ですが、そもそも有効論は積極的に唱えられていないというのが現状です。
憲法学のテキストをひもとけば、
現在わが国の法秩序を基礎づけているのが日本国憲法であることは、否定すべくもない事実である。(略)事実認識の問題として捉える限り、日本国憲法が無効であるとの議論にはあまり意味がない。
引用元:古野豊秋氏著『新・スタンダード憲法』(尚学社)
在日米軍の不法行為を許すのと同じ論理。法的根拠はないけれど、事実問題として米軍に特権を認めているから。許すんだ!という論理。
要するに、法的に考えることを放棄するという姿勢です。実は日本の憲法学者も「日本国憲法は法的には無効。しかし、事実問題として有効」という主張しかできないわけです。
帝国憲法第75条の類推解釈による日本国憲法無効論
南出喜久治氏は新日本国憲法無効論を唱えております(南出喜久治氏著『日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ』〔ビジネス社〕参照)。
南出氏は、大日本帝国憲法第75条「憲法及び皇室典範は摂政を置くの間これを変更することをえず」との条文に注目しました。
天皇が何らかの事情(ex.幼少や病気)で、国務(天皇大権など)を行えないときに摂政を置くのですが、
憲法改正の発議権は、天皇大権の一つ。摂政を含め、天皇以外の代理では許されない行為。
そのような「通常の変局時」でさえ憲法改正ができないのに、連合軍の完全軍事占領と言う極めて”異常な変局時”に、同条の類推解釈から考えて憲法改正は行えないとう主張です。
これは憲法限界説と同様に、国内法上からの日本国憲法無効論と言えるでしょう。
補足:日本国憲法有効論?「定着説」や「追認説」とは
事実問題として有効という説は、「定着説」とか「追認説」と言われることがあります。
たとえば、自衛隊を議論するにあたって、”憲法の変遷”が語られることがあります。
「改正手続きを経ないで、憲法の条文の語句はそのままで、憲法の意味内容が実質的に変化すること」です。
違憲の国家行為が反復・継続されることで憲法を改廃したことと同様の効力を持つ、という議論。このような議論を一部借りてきて、日本国憲法も「定着」したのではないか、という主張です。
ですが、憲法変遷自体が一般に肯定されたものではなく、学会の通説・多数説となっているわけではありません。
一体いつ「定着」したのか、その「追認」行為は誰のどのような行為を指すのか不明確だからです。そもそも憲法変遷と米軍による物理的な力の行使による憲法改正では次元が違うでしょう。
国会で日本国憲法無効宣言をすればよい
日本国憲法を無効とするには、衆院で憲法無効確認宣言をすればよいと言われています。
日本国憲法無効宣言がなされても、明治憲法第76条第1項には「法律規則命令はなんらの名称を用いたるに関わらず、この憲法に矛盾せざる現行の法令はすべて遵由(≒遵守)の効力を有す」とあるので、
刑法や民法などこれまでの基本的な法律の大部分は大日本帝国憲法下でも成立します。そもそも刑法や民法は戦前からほとんど変わっておりません。
大日本帝国憲法は、信教の自由、言論の自由なども認められていますので、基本的人権も充分に尊重されております。
兵役の義務など、一部国民生活に影響が出る部分もありますが、その点は慎重に判断していけばよいと思います。
弁護士や裁判官、国会議員など一部のエリート層は混乱するでしょうが、一般国民にはさほど大きな影響はありません。
まとめ
憲法学者は、法的には日本国憲法は無効、事実問題としては有効という苦しい主張。
日本国憲法無効論に関しては国際法上からの憲法無効論、国内法上からの憲法無効論があり、法的に極めて妥当な主張が存在します。
有効論に関しては、8月革命説という「政治色」があまりに強い有効論も一応ありますが、大半の憲法学教科書は、2~3行程度であまり触れようとしていません。
法的安定性を大事にする法学において、「革命」という言葉を結び付けるのはあまりにナンセンスだからでしょう。
もし本当にこんなことが起こり得るのであれば、英訳して全世界に大々的に発表すればいいのです。全世界の笑い者となりたくない日本の憲法学者は、誰もそんな愚かなことをしません。
憲法改正などは不要です。占領時の遺物である日本国憲法自体を破棄し、いまも現存する大日本帝国憲法を復元させればよいだけです(了)。


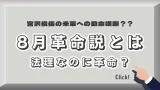


コメント