「日米戦争は無謀な戦いで、当時の日本政府は愚かな選択をした」
とくに分析もせず、結論ありきの議論が日本ではまかり通っています。
一方、欧米の学者の中には、日米戦はアメリカが日本に戦争以外の選択肢を残さなかったので、
日本政府は合理的に戦争を選択しただけという意見もあります。戦争とは時の運。米海軍もミッドウェー海戦で奇跡的な大勝利をするまでは勝敗は分からなかったはずだと。
戦前の日本同様、一般的に国家が冒険主義的に行動することはしません。
常にきわめて合理的、かつ冷静に判断しております。この点に関しては、欧米の学者の意見の方が正しいと思います。
では敗戦の理由はなんでしょうか。
まったく愚かしくて勝ち目のない戦争でないとすれば、その敗因はどこにあったのでしょうか。その点を考えないとしたら、そちらのほうがよほど愚かだと思います。
考えるヒントは、レイテ沖海戦における戦艦大和”謎の反転”がその一つ。栗田ターンとも呼ばれています。
実際、戦艦大和に乗船していた深井俊之助少佐(当時)が執筆された『戦艦「大和」反転の真相』(宝島社新書)には、栗田ターンの恐るべき真相が描かれております。
深井俊之助氏著『戦艦「大和」反転の真相』(宝島社新書)を参照しながら、現在も続く日本の行政・軍事組織の欠陥を2点あげてみたいと思います。
これらの点が改善されない限り、日本はあの戦争から何一つ学んでいないということになるのではないでしょうか。
この記事は、誰もが一度は聞いたことのあるレイテ沖海戦「栗田ターン 謎の反転」についても、わかりやすく説明しております。ご興味のある方はぜひお読みください。
レイテ沖海戦の謎の反転・栗田ターン
レイテ沖海戦とは、1944年10月20~25日。フィリピン周辺の広大な海域にて、日米の海軍艦隊の間で行われた海戦。
日本が優秀な戦闘機、パイロットともに失い、完全にアメリカ側に制空権を取られてしまい、勝ち目がなくなった戦争後期での作戦です。
帝国海軍ではこれ以後まともな作戦立案も出来ず、帝国海軍における最後の軍事作戦とも言われております。
作戦概要は、1944年10月、帝国海軍が戦艦「大和」「武蔵」を中心とした全戦力をもって、フィリピンのレイテ湾に上陸する米軍を叩くというもの。
具体的には、ハルゼー率いる米軍の主力空母含む機動部隊を、日本最強と言われた瑞鶴などの空母がおとり部隊としてレイテ湾より誘い出し、虎がいなくなったレイテ湾に「大和」らが突入するというものです。
米軍の輸送大部隊を戦艦の主砲で粉砕し、港を当分の間使用不能にする。米軍のフィリピン奪取作戦を遅らせるとともに、その上陸部隊も叩くことで米軍に大損害を与える作戦でした。
実は、この作戦は奇跡的に途中まで「成功」していました。
怪奇電報をでっち上げ、敵前逃亡する栗田司令
ハルゼーら米軍の機動部隊はまんまとおとりに誘い出され、戦艦大和がレイテ湾に突入する作戦がほぼうまく行きかけました。
しかし、作戦の最高司令官、栗田長官はそこで”謎の反転”をし、戦後も生き残ったのです。
もちろんレイテ湾に突入すれば、生還する可能性がほぼ無くなります。
燃料もそうですが、砲撃している間に足の速い米機動部隊が追いついてきますから。そんなことは作戦に関わった者は百も承知。反転の理由とはなりません。
栗田長官は作戦参謀とグルになり、怪奇電報をでっち上げ、逃げ帰ってしまったのです。この怪奇電報とは、レイテ湾突入前(南方への進路)に「北方に敵艦隊発見」という電報です。
結局、敵艦隊などおりませんでした。この謎の栗田ターンにより栗田長官ら戦艦大和は海域を脱出し、戦後も生き残りました。
一方、他の部隊は命を捨てて作戦に従事し、戦死しています。
この件に関しては、栗田長官をかばう声もあります。ですが、現実は、立派に戦死した者とおめおめ生き残った者。これがすべてを物語っているといえるでしょう。
深井氏は、これが謎の反転の理由であると喝破しております。しかし、敵前逃亡は銃殺刑が当たり前です。なぜこんなことがなしえたのか。
※こちらの記事は、当時作戦に参加していた深井俊之助氏著『戦艦「大和」反転の真相』(宝島社新書)を参照しております。ぜひご一読をお勧めいたします。
敵前逃亡を可能にさせた帝国海軍 2つの欠陥
たとえば、私が勤務先の会社からお金を盗み出すことは出来ると思います。
実際、社員として働いて、その金庫のロック番号も盗み見る機会が何度もあるからです。帳簿をごまかしてお金を不正に引き出すことだって出来ます。
ですが、それをしないのは業務上横領罪となり、犯罪事件として裁かれるリスクがあるからです。
ちゃんと罪に問われるから、そのようなことをしないのです。きっと読者の皆様もそうだと思います。
しかし、そのような前提が機能しない環境にあったのが、当時の帝国海軍の組織的欠陥でした。
機能していなかった軍法会議(1つ目の欠陥)
栗田長官は、レイテ以前の作戦でも敵前逃亡をしたと、軍法会議にかけられそうになったことがありました。
つまり”前科”もあり、栗田氏が司令官をすることは現場の指揮官らにとって大きな懸念材料でした。
しかし、深井氏が「上には甘く下には厳しい帝国海軍の在り方」と酷評しているように、この時も栗田長官は軍法会議で裁かれませんでした。
当時の帝国海軍は、命令違反を厳正に処分し、軍法会議で裁く環境になかったことが分かります。
栗田長官の人間性にも原因はあるでしょうが、これでは敵前逃亡する誘惑に駆られてしまうでしょう。
敵前逃亡は銃殺刑のような重罪に問われるのが当然ですが、まったくの無罪放免となるのです。現場が緩みっぱなしになるのは仕方ないでしょう。
物資や技術の問題ではなく、軍規や人事システムの欠陥
信賞必罰が原則。そのような軍法会議ではまったくなかった。栗田長官の敵前逃亡を生み出したひとつの要因だと思います。
本作戦は、何も砲弾が足りなくなったから断念したわけではないのです。砲弾は充分にあり、メカニックトラブルでもありません。
栗田長官が敵前逃亡を決めたから作戦が失敗したのです。もちろん物資不足や技術不足は戦争中いたる所で見られたと思いますが、本作戦の失敗はそれが原因ではないのです。
よく物量に勝る米軍に勝てるわけがなかったという話は聞きますが、物量の差など百も承知で作戦を立てています。
「あの会社には資本力で対抗しても勝てないから、技術力で勝負するんだ」という経営判断だってそうです。物量で劣るからもうダメだというわけではまったくありません。
レイテ沖海戦を見ても、戦争に敗戦した理由がもっと別にあるということが理解できるのではないでしょうか。
深井氏は、アメリカと違って日本は「能力のある人が上に立つような人事ではなかった」と実力主義の採用ではなく、年次や席次を優先する帝国海軍の組織的欠陥も敗戦の理由にあげております(深井俊之助氏著『戦艦「大和」反転の真相』〔宝島社新書〕参照)。
技術や物資(ハード面)の問題ではなく、行政上の人事システム(ソフト面)が敗因であるとする理由です。
上級交戦規定(ROE)の不明瞭さが作戦の失敗(2つ目の欠陥)
交戦規定(ROE)は作戦ごとに定められます。どこまでやって何をしていいのか、その点を明確にするのが交戦規定(ROE)を定める理由です。
まず政府や上級司令部(ex. 統合参謀本部)が本作戦のROEを決め、これが上級ROEとなります。
上級ROEを現場レベルにまでつなげていき、各レベルで下級ROEが決められます。
下級ROEは、その1つ上のROEの枠外に出てよいものではなく、1つ上の司令部の裁可を得てはじめて認められます。日本海軍のレイテ突入作戦は、上級ROEが明確でなかったことが反転の理由となりました。
本作戦の現場での作戦参謀の大谷氏(戦後参議院議員となり、平成元年逝去)は、当時、にこにこ顔で、
「司令部の作戦参謀から、もし途中で敵の主力部隊を発見したら、叩きに行ってもよいという許可が出たぞ~(これでいつでも逃げられる!!)」
という趣旨の発言を船内でしていたそうです(深井俊之助氏著『戦艦「大和」反転の真相』〔宝島社新書〕参照)。
つまり、レイテ湾に突入しなくてもよい口実が出来た。
要するに、途中で敵の主力部隊を発見したので、レイテ湾に突入しませんでしたという言い訳が出来るということなんです。
もうその時点で本作戦の上級ROEが不明確であることが分かります。
関東軍の暴走も交戦規程(ROE)が曖昧であったことが元凶
必ずやり遂げるべき作戦命令がこの時点でもう”ぶれている”のです。
上級ROEがそんな調子だから、現場で決められる下級ROEも自分たちの好きなように定めることが出来ます。
よく関東軍の暴走と言われますが、これも上級司令部の出す上級ROEがきちんと定まっていなかったからです。
だから、自分たちは作戦を自由に思い付きで実施できる。このような空気になってしまったのだと思います。
どっちつかずの命令を出しているのだから、「なにをどうしても罪には問えない」曖昧な状態が作られます。
「いやいや。自分たちは命令を守りましたよ。確かに○○という命令を受けていましたが、状況によっては××でもよいと言われていたので。だから僕たちは××にしたんです」と言えるわけです。
これが関東軍暴走と言われているものの正体です。関東軍が悪いのではなく、上級司令部、ひいては日本政府がちゃんと命令を出していなかった。方針を打ち出していなかったのが元凶です。
まとめ
栗田ターンと言われる栗田艦隊”謎の反転”の真相は、栗田長官が自分の命大事さに逃げ出した。敵前逃亡という重罪でした。
レイテ沖海戦以前も、栗田長官は敵前逃亡を噂されていた。前科もあります。
しかし、栗田長官の反転(敵前逃亡)を許したのは、本人の気質のみならず、
作戦の第一目標さえはっきりしない、いい加減な命令を上層部が発していたことも。これでは、現場の指揮官もきちんと守らないようになります。満州事変を起こした関東軍の暴走しかりです。
軍法会議も機能せず、上級の役職者はほとんど裁かれませんでした。
それゆえ、栗田長官たち、作戦参謀らは自らの命を最優先。戦場から逃走することしか考えませんでした。
もし交戦規程(ROE)が徹底され、軍法会議も機能していたら。レイテ沖海戦で反転しなかったら。歴史が大きく変わっていた可能性はあるでしょう。帝国海軍の組織的なニ大欠陥は、そのまま敗戦の2つの理由ともなっています。
2つはリンクしており、交戦規程(ROE)が不明瞭だからこそ軍法会議で言い訳が出来る。こんな状況で作戦が上手くいくわけがありません。
物資や技術というハード面ではなく、システム運用というソフト面でこそ劣っていたから負けたのです。なかなか目には見えにくいですが、先の大戦はソフト面で圧倒的に負けていたわけです。
戦後、日本は軍隊も持たず、ましてや交戦権も憲法上で認められていないため、交戦規程(ROE)を定めることさえ難しい状況となっております。
自衛隊の交戦規程(ROE)は、当時の帝国海軍よりもさらにあいまい。不明瞭。特別裁判所が禁じてられているため、軍事裁判所だってありません。
解決どころか、状況はさらに悪化しています。我々日本人はあの戦争から何も学んでいないのです(了)。
※こちらの記事は、当時作戦に参加していた深井俊之助氏著『戦艦「大和」反転の真相』(宝島社新書)を参照しております。ぜひご一読をお勧めいたします。
60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)
栗田ターンと言われる「謎の反転」は、作戦完遂よりも自分の命を優先した栗田司令官の偽計によるものであった。そう考えるのがもっとも説得力が高い。
他にも組織的な理由を2点あげると、ひとつは、上には甘く下には厳しいという帝国海軍の組織的欠陥。すなわち、敵前逃亡を裁き、作戦違反者を処罰する軍法会議。まったく機能していなかった(1つ目の理由)。
もうひとつは、上級交戦規定(ROE)が不明確。作戦における「○○が最優先目標であり、このような場合には△△をして~」というルールが曖昧であった。
なにをしてよいのか、どうとでも解釈できる余地があった。これにより、現場指揮官の作戦無視とも言える横暴や独走を止められなかった(2つ目の理由)。
日本がレイテ沖海戦含む、日米戦争に敗北した理由は、物資や技術の差といったハード面のみではなく、軍事・行政システムというソフト面で徹底的に敗北していたことが大きい。
もしレイテ沖海戦で反転しなかったら、米軍に大打撃を与えていたのは明白。歴史が変わっていた可能性もある。
現在の日本は、軍法会議など特別裁判所も持たず、国の交戦権も否認。当然交戦規定(ROE)も不明瞭となる。戦前よりもさらに状況は悪化している。

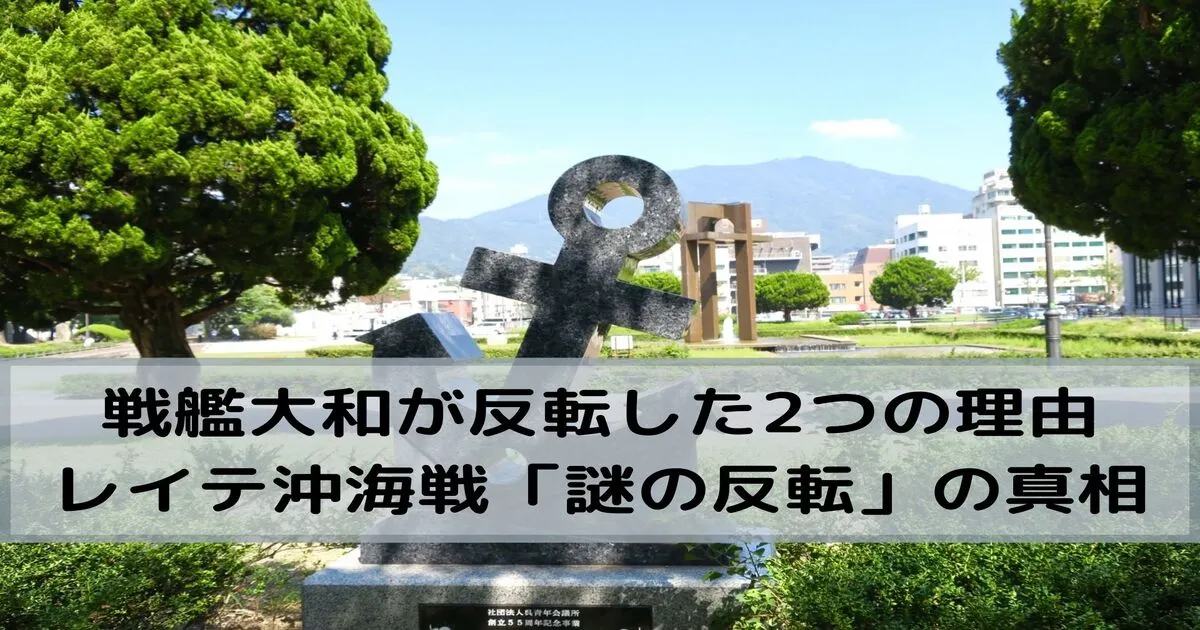
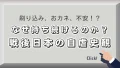

コメント