在日米軍の特権は数限りなく、文書としては在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定。また地位協定の協議機関である合同委員会の合意・議事録などで日米両政府で結んだもの。
ですが、合意や議事録は国防上の必要性からすべて国家機密。現在では特定秘密保護法により、特定秘密指定です。
もちろん国家安全保障の見地から秘匿される必要性もあるでしょう。しかし、在日米軍兵士の法的地位、身分、行政上の特権などは市民生活に関わるもの。
スパイ衛星が得た情報、暗号などの軍事情報はともかくとして、あまりにも非公表のものが多すぎます。
その中で、沖縄県は、諸外国との地位協定と比較し、HPで数多くの報告書を公開し、
日米地位協定は、他国の地位協定と比較し、不利な点が多いと発表しております(地位協定ポータルサイト-沖縄県)。
対して、日本政府の公式見解は、
他国との地位協定との比較においても、日米地位協定が接受国側にとり等に不利なものとなっているとは考えておりません
引用元:平成25年5月14日の参院予算委員会での安倍首相(当時)の国会答弁
沖縄と政府の主張が真っ向から対立する形となりました。今回は”欧州の在留米軍地位協定”と日本のものを比較しながら、果たしてどちらの主張が正しいのか。
実際に、欧州諸国の地位協定の条文とを見比べながら整理していきたいと思います。
『原則国内法適用なし』を主張する唯一の国・日本(日本のデメリット)
ヨーロッパには北大西洋条約(NATO)に基づくNATO軍地位協定があります。アジア諸国とは違い、イギリスやドイツ、イタリアなどはその同一の地位協定の下にあります。
また、地位協定には多国間と二国間の地位協定があります。
本来であれば、派遣国(米国)と接受国(受け入れ国)との従来の外交関係に基づき、それぞれの国に合わせた、独立した地位協定が結ばれます。これを二国間地位協定と呼びます。日米地位協定は、二国間地位協定となります。
ですが、ヨーロッパの主要国はNATOに加入しており、NATO地位協定という多国間地位協定がまずベースにあり、そのもとに各国がNATO地位協定を捕捉する協定などを、米国と個別に結んでいます。
よって、日米地位協定とNATO軍地位協定、及び各国の独自の補足協定を比較しながら検証していきたいと思います。
国際法上、駐留軍に国内法を適用するのが一般的(日本のみ例外)
まず、自国の国内法が駐留軍には原則不適用であるという立場を採っているのは日本だけ。極めて特殊。国際法上、駐留軍に国内法を適用するのが一般的な考え方だからです。
アジア・中東諸国の地位協定などを確認しても”接受国の主権を完全に尊重して”とか”接受国の主権に従属する”などの表現が、地位協定の条項によく出てくることからも明らか。
ところが、日米地位協定には日本の主権(sovereignty)という言葉はひとつも出てきません。第16条(日本法令の尊重)に米軍の日本法令の尊重義務が明記されているだけ。
他国の地位協定条文と比較し、日米地位協定は非常に異質なものです。
派遣国(米国)に自国の国内法適用なしと記載している該当箇所は、日米地位協定の条文にも存在せず、日本政府は、拡大解釈をし、地位協定の条文以上に米軍の特権を認めすぎています。
米軍になるべくフリーハンドを与えようとする不思議な国・日本
航空特例法など、日米地位協定で記載された米国の権利を国内法で認めるべく、日本は特例法をいくつも作っております。
原則は国内法が適用され、地位協定上で特に認められた部分のみが特例法によって米軍に認められると解するのが自然です。
もし原則国内法適用なしであれば、特例法等わざわざ作成する必要がありません。
ちなみに、自国の国内法不適用とは、自国の主権の範囲外に置くことです。他国ではありえないこと。
条約の拡大解釈により、米軍にフリーハンドを与えようとする政府の真意が理解できません。日米地位協定は総体的に、他国と比較し著しく不利なものといえるでしょう。
基地の管理権でも日本は圧倒的に不利(日本のデメリット)
基地や演習場に関し、日本は第3条で米軍に排他的管轄権を与えております。ですが、基地や演習場の外においても、その出入りの便宜を図るうえで米軍の要請があれば、日本側は関係法令の範囲内で必要な措置をとるものと定められております。他国の地位協定ではありえない!
条文解釈でも、米側は”もし必要な措置が執られなければ、米国側が独自に判断して対応するといったことに関して日本側は異議を唱えない”ことに言質を取っているそうです(米側の機密解禁文書)。
基地外でも米側の要求は基本的に通り、基地内においては完全に米側の管理権が及ぶ。
一方、NATO軍地位協定には基地使用に関して条文がありません。
各国それぞれが、ドイツならボン補足協定、イタリアならモデル実務取極(米伊了解覚書)などで、基地の国内法適用(≠排他的管轄権)を定め、基地への立ち入り権も明記しております。
米伊モデル実務取極第6条5では、「イタリアの司令官は、その責任に対応するために、基地のすべての区域に、いかなる制約も設けずに自由に立ち入る」。日本とはだいぶ温度差があります(沖縄県の『地位協定ポータルサイト』など参照)。
低空飛行訓練等は規制の対象となる諸外国(日本のデメリット)
米軍機に対する爆音被害での対応に関しても、日本とヨーロッパ諸国ではまったく異なります。
日本では米軍による訓練や演習についてもなんら規定がなく、低空飛行訓練や基地でのストップ・アンド・ゴーでの爆音・轟音被害に関しても日本側の管轄外となっております。
裁判所でも第三者行為論といった法理が認められ、爆音・轟音被害者による米軍の飛行訓練中止を求める訴えは退けられています。
米軍は日本政府にとって「第三者」であり、日本政府が訓練を中止させられなくとも責任はないという判例が確立しております。
ヨーロッパ諸国では米軍の空域利用を厳しく制限!
欧州諸国では、各国の補足協定や国内法で米軍機の航空利用をきわめて厳格に制限しております。
ベルギーでは、国内の飛行規則をまとめた航空路誌(AIP)で、自国軍機よりも外国軍機に対しより厳しい規制。
ベルギーの航空路誌1.2.4には「土曜日、日曜日及び祝日においては、通過を除くそのほかの飛行が禁止されている。ベルギー軍航空部隊は、本規則から除外される」。
英国でも駐留軍機の飛行は、英空軍の規制方針の遵守が求められます。
英国空軍規制方針規則RA2307 73 では「必要な場合、英国防省は、英国の飛行情報区又または上層飛行情報区内の全ての空域における、英国軍の航空システムまたは駐留軍の航空システムの飛行に関し、禁止または制限する、あるいはこれに条件を課すことができる」というもの。
日本と違い、低空飛行訓練等はもちろん認められない(日本のみ例外)
在欧米空軍が作成した在英米軍の飛行運用に関する指令書にも、米空軍のさまざまな活動に際し、英国防省の承認が必要であることが規定されております。
在欧米空軍指令書8.1では「英国国防省による書面での承認が与えられている場合を除き、英国外を拠点とする米軍航空乗務員による低空飛行は禁止されている」。
日本と違い、米軍の国内での演習場等での訓練に対して許可制を採っているヨーロッパ諸国。
低空飛行のような危険な訓練は不許可とし、自国で行わせない。
航空機の墜落事故に関する各国の警察の捜査においても、日本側は米軍に内周規制線を張られてしまい、警察はその中には立ち入ることができません。
一方、各国は国内警察が証拠品を押収するなど主体的に捜査が行われその優先権が認められております。
米国が日本で低空飛行訓練を熱望する理由は、他国では、そのような危険な訓練の許可が下りないからです。もちろん、米国本国でも、米国市民を危険にさらすような訓練は行えません。
まとめ
国内法が原則不適用という異常な状況。低空飛行訓練の規制や基地内への強制的な立入権などもない日本。日米地位協定は、ヨーロッパ諸国よりも著しく不平等な在留米軍地位規定です。
たしかに日本とNATO諸国との地位協定で変わらない点もあります。
税関や為替管理、本国での自動車運転免許証の接受国での有効性などに関しては、特に規定は変わりません。
派遣国である米軍人は出入国において旅券パスポートや査証に関する規制が免除されて、外国人登録なども不要です。他にも、日本政府が刑事裁判権に関してNATOと変わらないと主張しますが、これは「条文上」の規定をみれば本当のことです。
ヨーロッパでも公務中の犯罪は米側に第1次裁判権がありますし、派遣国の手中にある間は被疑者の拘禁(拘留)は起訴されるまでの間、派遣国により引き続き行われます。NATO軍地位協定では第7条、日本では第17条に条文があります。
ただし、日本では裁判権放棄密約を裏で結び、米軍の犯罪に対して第1次裁判権をたとえ持っていても放棄してしまうという問題。
基地内はいうに及ばず、たとえ基地外でも米軍の財産であれば押収できないという捜査上の制約などが多く、協定上の条文以外で結ばれた様々な合意や議事録によりヨーロッパ各国よりも不平等な点が多い。
一部研究者が、米国の公開情報をもとに密約を一部暴き出しております。
よって、沖縄県の主張「日米地位協定は他国と比較して不利である」は全面的に正しいと言えるでしょう(了)。
※アジア・中東の地位協定の比較もしております。ぜひこちらもお読みください。

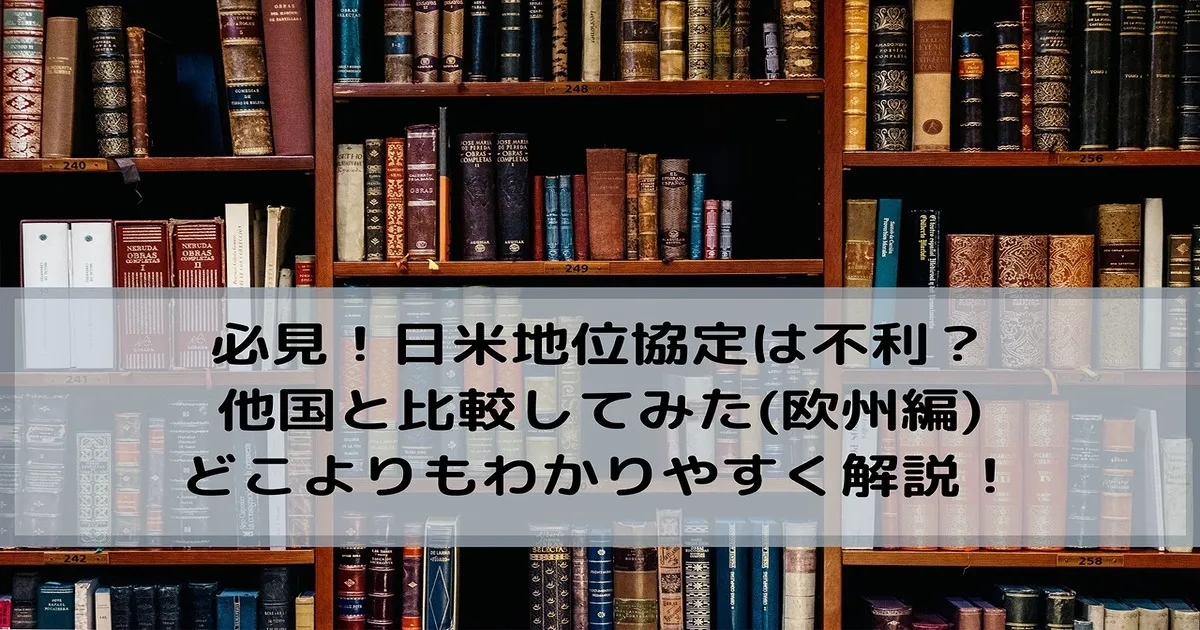
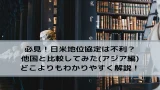


コメント